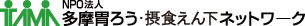米国の高齢者
終末期医療への心構え 指示書や代理人を通して意思表示 |
| 自分がどのような最期を迎えたいかを家族や主治医に伝えている人は、きわめて少ない。自分の死について考えることなど、縁起でもないと思ってしまうからだ。 終末期の医療のあり方について、意思表示ができなくなった時に備えて、あらかじめ代理人を選定、延命治療を拒否するなどを表明しておく方法として、アドバーンス・ディレクティブズ(事前指示書)がある。しかし、米国でも75%は、その存在すら知らないという(AHRQ=Agency for Healthcare Research and Qualityの2009年の調査)。同様の調査を私たちも2007年に行ったが、事前指示書を知っていたのはわずか7%、既に用意していたのは1%でしかなかった(健康セミナーの参加者など約500人が回答)。在宅での終末期医療が注目をされているが、まだまだ心構えが不十分だ。 病院では、食事、起床、消灯の時間が決められるなど自由に生活することは難しいが、緊急時への対応が保障されている。自宅に戻ると、より人間らしい生活を取り戻すことができるが、その分、自己責任で対応しなければならないことが増える。在宅医療の成否は、いかに自立した患者になるかにかかっているといえるが、日米でのアンケート調査結果は、老い支度が十分でない人が多いことを教えてくれる。自分がどのような終末期医療を望んでいるかをはっきりと表明することが、第一に必要だ。 事前指示書によって、ICU(集中治療室)に入り意思表示ができなくなった患者の代理人になった人を対象にした2010年の調査(ピッツバーグ大学)では、延命治療の中止の決定を医師任せにするとの回答は5%でしかなかった。代理人である自分が決めるが55%、医師と相談して決めるが40%だった。医師と代理人との信頼関係がしっかりしているほど、また男性やカトリックの代理人ほど、患者のために自分で決定をしたいという思いが強いこともわかった。事前指示書を用意し、しかるべき代理人を選定することが、終末期を在宅で迎えるための必要条件ともいえる。 |
| 日刊工業新聞 2011年2月4日 |