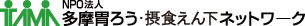日本の高齢者
終末期の在宅医療 家族の思いと本人の気持ちを調整 |
| 「病気になって、初めて健康のありがたみを知る」というが、同様に老い支度の準備も、困ったことが起こるまでは考えたくないというのが実情ではないだろうか。そして最期は、自宅で迎えたいと多くの人が漠然と願っている。 在宅医療助成勇美記念財団の市民公開講座に参加した人を対象にした2008年のアンケート調査によると、最期を迎えたい場所の順位は、①自宅51%、②ホスピス20%、③介護施設15%、④病院10%となっている。しかし、家族には余分な負担をかけたくない、緊急の治療が必要になった時が不安などの理由で、結局病院に入院、90%近くが病院で亡くなっているというのが現状だ。 訪問看護ステーション制度の発足と同時に、在宅ホスピスを中心とした訪問看護に従事してきた看護師の秋山正子さん(白十字訪問看護ステーション)は、家族が納得できるように訪問看護が介入、かかりつけ医と連携が上手に取れ、ヘルパーとの協働による生活支援、緊急時の連絡体制が確立すれば、終末期の在宅医療は可能となるという。そのために、訪問看護師の第一の仕事は、「看取りの経験がなく、親の死を現実的にみることができず、いつまでも生きて欲しい思う家族と、穏やかな在宅死を望む本人の気持ちを調整すること」と語る。 東京都新宿区は、2009年度から在宅療養体制の整備を高齢者保健福祉計画の重点策の一つとした。一般の人ばかりではなく、急性期病院に働く医療者も、病院でなければ死ねないと思っているところがある。その第一歩として、がん患者の退院調整を担っている看護師を中心に、訪問看護ステーションで研修を行い、在宅における終末期医療も選択肢の一つであることを認識してもらっている。また区民への啓蒙のため、公開講座では、看取り経験者に講師となってもらう。家族の体験は感動を呼ぶばかりではなく、理想論ではない現実の話としての説得力がある。遺族も、語ることによって癒される。少しずつではあるが、在宅医療の輪が広がろうとしている。 |
| 日刊工業新聞 2011年1月21日 |